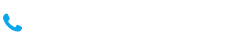新たなマイバッグ使用システム

CEEAでは、「共有リユースバッグ※1」「究極のマイバッグ※2」といった新たなマイバッグシステムが、秋田県におけるレジ袋削減・マイバッグ推進の「軸」と成り得るか、また「軸」となるために必要な導入方策の他、既存のレジ袋削減・マイバッグ推進方策を取巻く状況などについて調査・検討を重ねてきました。この検討は、CEEAによる調査方法、結果、考察について、学識経験者や事業者、消費者団、自治体等から構成される『新たなマイバック使用システム作り検討委員会※3』から評価や意見を受ける形で行われました。
この調査・検討を通じて、マイバッグ推進・レジ袋削減についての主体性の乏しさこの取り組みの閉塞感が漂う一因である可能性が再確認され、新たなマイバッグシステム(特に「究極のマイバッグ」システム)は、この閉塞感を打破する可能性を秘めているとの結論に至りました。
また、新たなマイバッグシステムを含む、秋田県全域でのレジ袋削減・マイバッグ推進へ向けて消費者、事業者、自治体の皆様に対して以下をお願いしたいと考え、提言としてまとめました。
「究極のマイバッグ」について調査結果
消費者687名、20事業者、24自治体を対象に、マイバッグの「色」「形」「生地」「価格」に対する意向調査を行いました。
結果は、ここをクリック!
「共有リユースバッグ」についての調査結果
「共有リユースバッグ」については、他の人が使ったバッグへの抵抗感が消費者に根強く、事業者・自治体についてもこのシステムの消極的でした。これらの結果を受けて、「共有リユースバッグ」の普及・定着は困難と判断しました。
マイバッグ推進へ向けての提言
【消費者へ向けて】
レジ袋削減・マイバッグ推進の主役であることから・・・
- レジ袋削減・マイバッグ推進に関心を持ち続けること。
- 自分なりにレジ袋削減の工夫をし、実践すること。
【事業者へ向けて】
レジ袋削減・マイバッグ推進の大きな流れを生み出す立場であることから・・・
- 県内や県内各地域のレジ袋削減・マイバッグ推進の議論の場に積極的に参加し、意見を示すこと。
- 海外や国内には事業規模や形態に応じた様々な取り組みが存在することから、積極的に情報を取集し、主体的に実践すること。
【自治体に向けて】
レジ袋削減・マイバッグ推進の地域における推進役であることから・・・
- 域内の積極的もしくはユニークな取り組みを行っている事業者を目立たせるような普及啓発を展開すること。
- これまでの単一の自治体による域内への「呼びかけ」から、周辺自治体を含む広域的な取り組みとしての「呼びかけ」を実施できる体制を構築すること。
秋田県、市町村別には以下を提案します。
<秋田県>
自治体同士が横断的に意見や情報を交換ができる「場」を創出し、ここでの意見や集約された情報を「レジ袋削減・マイバッグ推進運動協定」参加事業者と共有することを提案します。
<市町村>
自治体意見交換会に参加し自らの意見を示した上で、市町村間の連携の方向性を模索し、広域的な取り組みとして消費者・事業者への参加・協力の呼びかけを行うことを提案します。